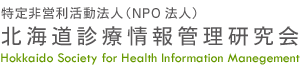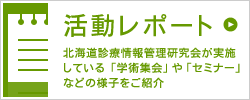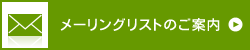第176回北海道診療情報管理研究会学術集会(報告)
【作成日】:令和7年9月24日
【報告者】:内田 諭志 【施設・部門名】:我汝会えにわ病院 診療情報管理室
【開催日時】
第176回北海道診療情報管理研究会学術集会
令和7年9月13日(土)13時30分~16時10分
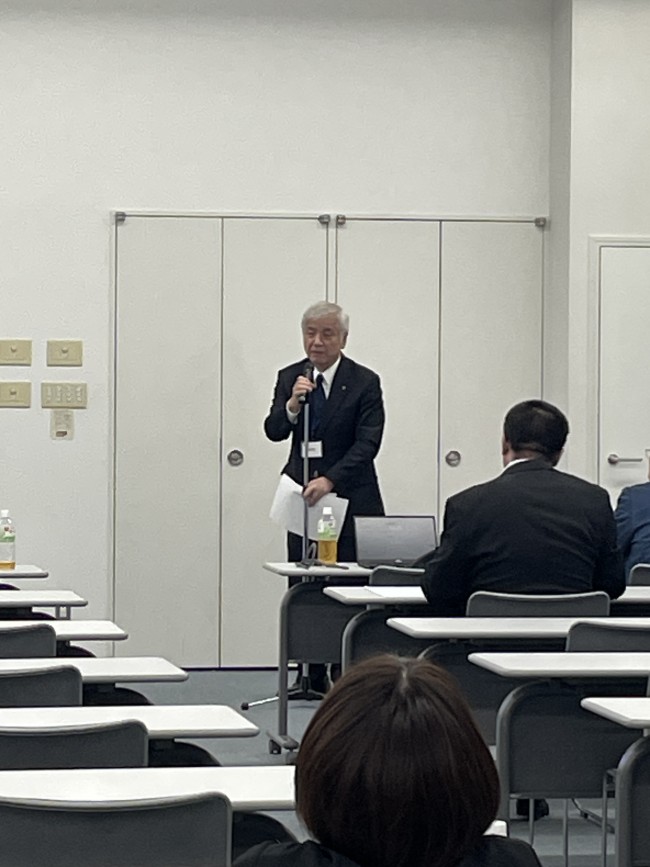
【講演1】
タイトル:「医療の質を“見える化”するデータ基盤整備と統計解析の力 -診療情報管理士に求められる視点と実践力-」
講 師:山梨大学大学院総合研究部医学域臨床医学系特任教授・同附属病院病院長補佐 小林 美亜 様
【講演1】1.講義内容紹介
医療の質は目に見えにくい概念であり、患者・医療者・経営者それぞれが異なる視点を持つため、共通の指標で「見える化」することが重要であると述べられました。そのために臨床指標を活用し、現状把握、要因分析、改善につなげる仕組みが必要であることが示されました。
ご講演では、ドナベディアンモデル(構造・過程・成果)を用いた評価の考え方や、診療報酬制度における質評価の位置づけ、また平均値と中央値の使い分け、四分位範囲を活用したベンチマーキングの具体例などが解説されました。さらに、転倒・転落や身体的拘束の評価・改善活動など、日常業務に直結する事例も多く紹介されました。
また、電子カルテの限界やデータの二次利用の課題、DX推進における「現場の声を反映したシステム設計」の重要性についても言及がありました。単にデータを集めるのではなく、改善につなげる活用こそが診療情報管理士の役割であると強調されました。
【講演1】2.学んだこと
今回のご講演を通じて、医療の質を客観的に評価するためには臨床指標を基盤とし、構造・過程・成果の三側面から分析するドナベディアンモデルの活用が有効であることを学びました。さらに、平均値と中央値の使い分けや四分位範囲による比較といった具体的な統計手法が、単なる数値の提示にとどまらず、改善の方向性を示すための重要な視点であることを理解しました。また、電子カルテの限界やデータ二次利用の課題を踏まえ、データの質を担保することと、現場の声を反映したDX推進の必要性も改めて認識しました。
【講演1】3. 業務に活かしたい点
日常業務においては、転倒・転落や身体的拘束の評価・改善といった具体的な臨床事例を参考に、収集したデータを分析して改善活動へと結びつける取り組みをより意識的に行いたいと思います。特に、統計的な手法を用いたベンチマーキングを活用することで、自施設の位置づけを明確にし、他施設との比較から改善点を見出す実践を進めたいと考えます。また、DXの推進に際しては、単なるシステム導入にとどまらず、現場に即した改善につながる設計を意識し、診療情報管理士としての専門性を活かして提案できるよう努めたいと思います。
【まとめ】※感想など
今回の講演を通じて、私たちは診療情報管理士が担うべき専門性と実践力を改めて認識しました。特に、データの収集から解析、そして改善へとつなぐ一連のプロセスにおいて、診療情報管理士が果たす重要な役割を再確認する機会となりました。

【講演2】
タイトル:「データ主導社会における統計が開く医療の未来 -変革の担い手としての診療情報管理士-」
講 師:総務省政策統括官付 国際統計管理官 永田 真一 様
【講演2】1.講義内容紹介
行政官として国内外の幅広い政策に携わった経験をもとに、統計と医療データの持つ力について多角的に解説されました。統計は国の政策判断の基盤であり、SDGsやWell-beingといった国際目標においても重要な役割を果たしていること、日本が提供する医療関連データが国際比較や指標作成に反映されていることが紹介されました。また、統計の信頼性を損なう事例が国内外で問題となってきた経緯に触れ、正確で透明性の高い統計こそが国民生活を守り、国際的信頼を築くために欠かせないと強調されました。
医療分野に関しては、抗菌薬耐性菌の割合や疾病負荷の分析など、診療情報管理士が関わる日常のデータがSDGsの進捗評価やWHOのデータベースに活用されている実例が示されました。さらに、人口減少と人手不足が進む中で医療DXの推進は不可欠であり、電子カルテの全国普及やデータ基盤の標準化、マイナンバーカードを活用した医療情報の連携などが国策として進められていることが述べられました。その際、単なるシステム導入ではなく、業務全体の設計を見直し、効率的で質の高い医療提供につなげる必要性が指摘されました。
最後に、診療情報管理士が収集・管理する正確なデータは、医療政策や国際交渉を支える基盤であり、今後は情報セキュリティや国際標準化への対応も含めて、社会の変革を担う重要な役割を果たしていく存在であると結ばれました。
【講演2】2.学んだこと
今回のご講演を通じて、診療情報管理士が扱う日常的なデータが国内の医療政策だけでなく、SDGsやWHOの国際指標といったグローバルな枠組みにまで直結していることを学びました。統計の信頼性が国の政策判断や国際的な信頼に直結すること、また透明性の高いデータ管理が国民生活を守る要となることを強く認識しました。さらに、人口減少や人手不足が避けられない状況において、医療DXを単なるシステム導入にとどめず、業務設計の見直しを伴う「改革」として推進することの重要性を理解しました。
【講演2】3. 業務に活かしたい点
日々の業務においては、統計的な正確性と信頼性を意識し、収集・管理するデータが将来的に国際比較や政策立案に利用され得るという視点を持ちたいと考えます。特に、抗菌薬耐性菌などのテーマは自施設のデータ収集にも関連が深く、質の高い入力・管理が医療の改善だけでなく国際的な課題解決にも寄与するという意識を持ち続けたいと思います。また、DX推進の中では、現場の業務効率化や医療提供体制の質向上につながるよう、単なる「電子化」ではなく全体最適を意識した運用改善の提案に取り組みたいと考えます。

【まとめ】※感想など
今回の講演は、診療情報管理士の業務が国内外に大きな影響を与えていることを改めて実感する、大変貴重な機会となりました。
(記録記載者;えにわ病院 内田 諭志)